受動喫煙被害者は、我慢や回避をしている! 東京都の調査から(後編)
[本記事は、受動喫煙撲滅機構の関係団体による執筆です]
前回5月9日の前編 受動喫煙被害の多い場所はどこ? 東京都の調査から(前編) の続きです。
前編においては、受動喫煙が多く発生している場所である「路上」と、「飲食店」に着目しました。
引き続き、平成 29 年度 受動喫煙に関する都民の意識調査 報告書 を見ていきましょう。
受動喫煙の被害に遭った人たちの行動は?

実際に受動喫煙の被害に遭ってしまった人たちが、どのような行動をとっているのかに関して、以下の調査結果がでています。
問13 あなたはこれまで受動喫煙にあったとき、どのような行動をとりましたか。次の中から当てはまるものをすべて選んでください。(○は当てはまるものすべて)
1 喫煙者に喫煙を控えてもらうよう頼んだ
2 自分が席や場所を移動した
3 自分が我慢した
4 気にならなかったため、何もしなかった
5 受動喫煙にあったことはない
6 その他( )—–
受動喫煙にあったときの行動では、「自分が席や場所を移動した」62.4%、「自分が我慢した」61.7% の2 項目が他よりも極めて高くなっている。
| 行動 | 割合 |
| 自分が席や場所を移動した | 62.4% |
| 自分が我慢した | 61.7% |
| 喫煙者に喫煙を控えてもらうよう頼んだ | 5.7% |
実に、3分の2ほどの被害者が、回避行動を取るか、我慢をしています。
喫煙者に対しての行動をとったのは、5.7%に過ぎません。
受動喫煙って、「我慢するもの」?「回避するもの」?
受動喫煙は、本来、絶対に「発生させてはならない」ものです。
「嫌がるなら、煙から逃げればよい」ではなく、もともと受動喫煙が発生しないシステムが求められます。
喫煙者は、受動喫煙が発生しない喫煙行動を取る必要があります。
ですが、実際に受動喫煙の被害に遭った人々の多くは、回避か我慢をしています。
無用なトラブルを避けたく、直接注意をしたくない心理は、十分に理解できるものです。
被害者の望みは?
そんな受動喫煙被害者たちの望みに関しても、調査が行われています。
問18 受動喫煙防止対策を進めていく上で、法的な規制(法律・条例等)について、どのようにお考えですか。次の中から1つ選んでください。(○は1つ)
1 施設に対して「法的な規制(法律・条例等)がある方が良い」⇒問18-1、18-2 へ
2 施設に対して「法的な規制(法律・条例等)はしてほしくない」⇒問18-3 へ
3 わからない ⇒問19 へ
(問 18 で「法的な規制(法律・条例等)がある方が良い」と回答した方)
問 18-2 どのような規制が良いと考えますか。次の中から1つ選んでください。(○は1つ)
1 国が全国一律の罰則付き法律を制定する
2 国が全国一律の罰則なしの法律を制定する
3 東京都及び区市町村が独自の罰則付き条例を制定する
4 東京都及び区市町村が独自の罰則なしの条例を制定する
5 その他
—–
(3)望ましい規制内容
「国が全国一律の罰則付き法律を制定する」が 57.9%で最も高く、半数以上を占めている。次いで、「東京都及び区市町村が独自の罰則付き条例を制定する」が 29.1%となっており、この 2 つを合わせた『罰則付きの規制』を求める割合は 87%に上っている。
罰則付きの規制を求める割合が87%
罰則付きの規制を求める割合が87%という結果は、
受動喫煙の問題を、吸う人や、受動喫煙の被害にあった個人の問題ではなく、社会の問題とし、
社会の取り組みとして受動喫煙を無くして欲しいという、被害者の気持ちの現われだと言えるのではないでしょうか。
プライベート空間の喫煙対策
最後に、路上や飲食店ではない、自室や自家用車内といったプライベート空間での受動喫煙に関する意識調査を見てみましょう。

問21 プライベート空間(家庭内・自家用車)での喫煙において、対策が必要だと考えるものはどれですか。次の1~6の中から選んでください。(○は当てはまるもの全て)
また、1~4を選択した場合は、それぞれ①~③を選んでください。(○は1 つ)1 未成年者がいる車内での喫煙 ⇒①罰則付きの規制が良い ②努力義務の規制が良い ③規制は不要
2 妊婦がいる車内での喫煙 ⇒①罰則付きの規制が良い ②努力義務の規制が良い ③規制は不要
3 未成年者がいる家庭内での喫煙 ⇒①罰則付きの規制が良い ②努力義務の規制が良い ③規制は不要
4 妊婦がいる家庭内での喫煙 ⇒①罰則付きの規制が良い ②努力義務の規制が良い ③規制は不要
5 家庭や自家用車のようなプライベート空間における規制は不要
6 その他 ( )—–
プライベート空間における対策の必要性については、「妊婦がいる車内での喫煙」が69.8%、「未成年者がいる車内での喫煙」が69.1%、「妊婦がいる家庭内での喫煙」67.6%、「未成年者がいる家庭内での喫煙」67.1%の順となっており、いずれも6 割を超えている。
性別・年齢別・喫煙状況別では、特に大きな差はみられなかった。
ここで、あれ? と思いました。
子どもと妊婦だけが対象で、妊婦ではない配偶者(男性も含みます)や、成人している住人がいる家庭が該当する選択肢がありません。
「妊婦、未成年にかかわらず、プライベート空間での喫煙 ⇒ ① 罰則付きの規制が良い ② 努力義務の規制が良い ③ 規制は不要 」
という、選択肢があってしかるべきではないでしょうか…?
いわゆる“社会的弱者”に着目することは重要ですが、子ども・妊婦以外は考慮しなくてよいものでしょうか?
家庭内であっても、受動喫煙は絶対に駄目であると考える人は、どれを選べばよいのでしょうか。(6のその他になるのでしょうか?)
引き続き、調査結果を見てみましょう。
「未成年者がいる車内での喫煙」を見てみます。(画像はクリックで拡大します)
「規制は必要だが、努力義務でよい」と考える人が50%強です。
問18-2の回答においては、「罰則付きの規制」を求める割合が87%であったのに対し、
「車内」と限定したこの設問においては、より弱い立場の未成年者が被害者であっても、「罰則付き」を望む割合51.7%と、下がっています。
これをどう理解すべきか難しいところですが、
「親が吸うのであれば、子どもが受動喫煙に遭うのは、ある程度しかたがない」ということなのでしょうか?
もしくは「プライベート空間に法令は及ぶべきではない」ということなのでしょうか。
子どもの受動喫煙は特に問題=被害が大きくなりやすい でも言及しましたが、子どもは受動喫煙の被害に遭いやすく、また、被害が深刻化・長期化しがちです。
保護者の変化を待つのではなく、子どもの救済が最優先ではないでしょうか。
そして、被害に遭っている子どもを受動喫煙から解放するためには、行政の介入も重要であり、その介入の根拠としても罰則は、重要なのではないかと考えます。
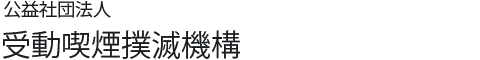



何かの研究にしてもアンケートにしても、数値を出すとき「健康な人」を対象に数値を出していませんか?
現在は入院日数も少なくなり、病気を持った人も日常生活をしています。
日本人の死亡原因第1位は癌と言われています。
タバコは発がん性物質が20種類以上含まれていますよね。
健康な人が癌になりたくないように、癌患者は再発をしたくない方がほとんどだと思います。
退院をしたからといって普通の生活に戻れるように努力されている方、再発したくない方、発作が起こらないように気を付けている方など、色んな方が生活をしていらっしゃいます。
その方の意見が優先されるべきです。
その方達が生活ができる環境でなければ、健康な人を対象にされても健康なのですからすぐには病気にならないと思います。
上記の結果からも、健康な人でも受動喫煙を受けたくない事が分かります。
しかし、病気を持たれた方を対象にすると100%に近い数字が出るのではないでしょうか?
この結果では「病気の人は対象外なので我慢しろ」と言っているように見えます。
癌からアレルギーに至るまで、病気を持った人が日常生活をしていて、どの病気の人がどのような影響を受けるのか、それを対象に考えた上で喫煙所の設置の仕方、受動喫煙の規制、タバコ販売に至るまで議論されなければいけないと思います。