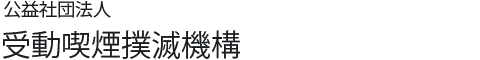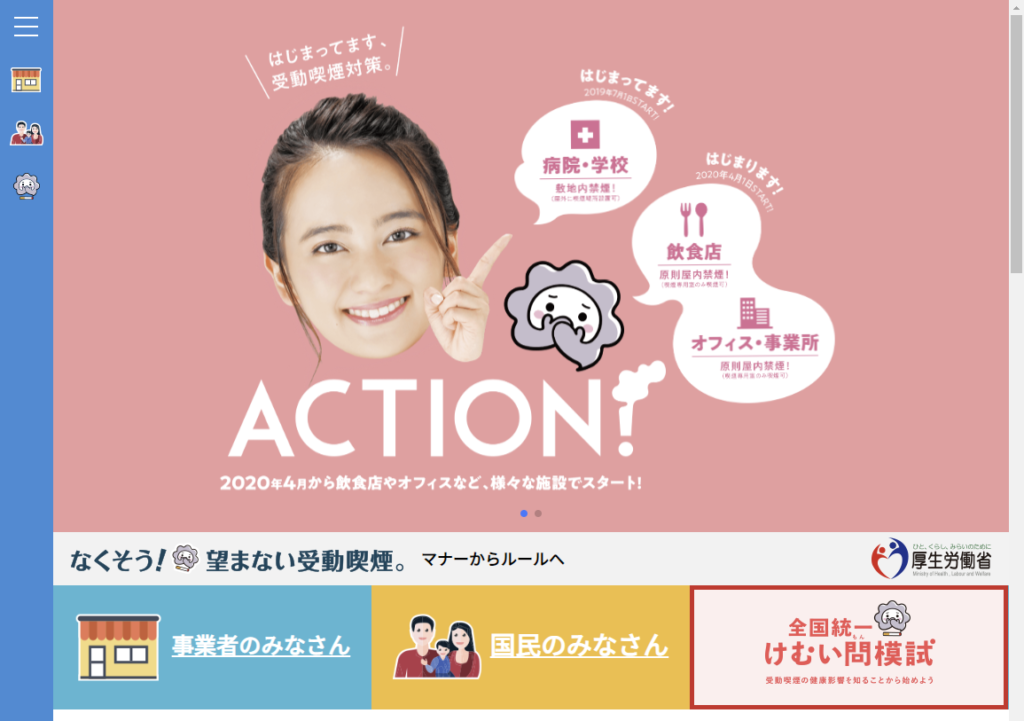受動喫煙への対策その1 – 職場での受動喫煙
[本記事は、受動喫煙撲滅機構の関係団体による執筆です]
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、いよいよ受動喫煙を防止するための施策が、ルール化されます。
[当サイトいままでの関連記事](他にもあります。右窓で検索できます)
「健康増進法 改正案」可決 問題は ~各報道
職場の禁煙・受動喫煙対策はどう変わるか? 「改正健康増進法成立」を産業紙が解説
小学生にもよくわかる「受動喫煙防止法」(改正健康増進法) 成立
喫煙はマナーからルールへ「健康増進法の一部を改正する法律」について
ですが、職場では、いまだに受動喫煙の被害に遭っている人が、たくさんいるのが現状です。

泣き寝入りする必要はありません。
我慢する必要はありませんし、自分の健康のためにも我慢すべきではありません。
打てる手があります。
法令で受動喫煙にまつわる規則が厳しくなってきたのは、ニュースで聞いたことがあって、具体的に法令がどう変わって、どのようにすれば事態が改善されるのかは、なかなかわかりません。
ここでは、改めて法令を確認しながら、取りうる対策について整理して行きたいと思います。
なお、今回は話を単純にするために、屋内での受動喫煙に限定します。また、健康増進法以上に厳しい条例を制定している自治体もありますが、ここではおいておきます。
まずは法令の確認
何が禁止され、何が許さるのかを、正確に把握しましょう。
わからなくなった際に、曖昧な情報に惑わされることがないように、情報源(どこからの情報か)にも配慮しましょう。
まず目を通したいのが、厚生労働省のガイドライン です。
通常のオフィスは、第二種施設に該当することが多いと思います。
次に、「なくそう!望まない受動喫煙。」Webサイトの 飲食店/事業者のみなさん にも、目を通しましょう。
目を通していただくと、「屋内禁煙」の原則がわかると同時に、
そもそも、受動喫煙は健康被害を発生させるという、極めて重要な点も確認できます。
原則屋内禁煙
すぐに分かるのは、「原則屋内禁煙」だということです。
「当社は喫煙しながら仕事をするのが長年の文化だから・・・」などという話ではなく、屋内は禁煙です。
会社の方針以前に、法律です。
守らなければなりません。
敷地内では、一切喫煙できないの?
「喫煙専用室の設置が可能」です。
喫煙専用室の種類や、「そこで飲食ができるか」に関しては、「設置可能な2つの喫煙室」を御覧ください。
確認ですが、原則屋内禁煙です。
喫煙が可能なのは「喫煙専用室」だけです。
どんな義務がある?
施設管理者には、以下の義務があります。
1.喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
2.標識の設置
3.各種喫煙室の基準適合など
罰則はある?
あります。
施設管理者に対しては、
違反した施設管理者には最大50万円
などの罰則があります。努力義務ではありません。
なお、喫煙者に対しても、最終的には罰則が適用されます。
第二十五条の五 何人も、正当な理由がなくて、特定施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
2 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。第四十一条 第二十五条の五第二項の規定に基づく命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
健康増進法の一部を改正する法律案
詳しくは、ポイント9の「義務違反時の指導・命令・罰則の適用について」を御覧ください。
いざ受動喫煙が発生した際には
屋内で受動喫煙被害が発生している場合には、いくつかのパターンがあります。パターンごとに対処を整理しましょう。
ここで重要なのは、もし仮に、「一部の喫煙者がルールを守らないがために受動喫煙が発生している」と、あなたが感じたとしても、決して「自分でその個人を変えよう」とはしないことです。
施設管理・就業環境の整備の問題と捕らえ、施設管理の徹底を考えてください。
受動喫煙の被害に遭えば、どうしても頭に来ますが、どうか冷静になって、「喫煙者」ではなく「施設管理」、事業所側の問題だと捉え直してください。
ヒトではなく、施設管理、環境を変えていきましょう。
※なお、施設管理に問題がなく、特定の喫煙者がルール違反を繰り返す場合には、
法律違反ということで、喫煙者自身に罰則が課される(最大30万円の過料)ことになるでしょう。
パターン1 ルールが無い?室内で自由に喫煙している
あたかも、室内禁煙のルールが無い”かの”ように、皆が自由に室内で喫煙しているパターンです。
(法律があるので、もちろんルールはあります)
とんでもない状態ですが、多いのではないでしょうか。
ポイント:その施設では、受動喫煙対策が行われていない。法律違反の状態
対策: 施設管理者に、受動喫煙対策の義務があることを認識してもらい、改善してもらう。
被害の状況(受動喫煙が発生していること)を、具体的に(いつ誰がどのような)報告し、法令違反状態ある旨を理解してもらいましょう。
施設管理者へ報告する前や途中で、行政に相談するのも良いでしょう。
パターン2 ルールはあるがあまり守られていない
施設管理者に尋ねれば「室内禁煙」という回答を得るが、実際には室内で受動喫煙の被害が多発している。
室内禁煙のルールは明確に存在しているが、守られていない状態です。
ポイント:全体的にルールが守られていない
対策:施設管理者に、ルールが守られるように改善してもらう
ルールが守られない背景には、認識しているけども守らない人(確信犯)と、認識がない人が混じっていることが多いです。
確実に認識してもらうために、よりはっきりと室内禁煙の掲示をし、ルールを守らない喫煙者への注意をしてもらいましょう。
施設管理者へ報告する前や途中で、行政に相談するのも良いでしょう。
パターン3 特定少数の喫煙者が受動喫煙を発生させている
喫煙者の大半は、室内禁煙のルールを守っているが、特定少数の喫煙者がルールを守らず、受動喫煙被害を発生させているケースも多いです。
室内禁煙の認識があるのに、守っていないケースです。
ポイント:室内禁煙の告知は十分である。特定の喫煙者が受動喫煙を発生させている。
対策:施設管理者を通じて、その喫煙者の室内禁煙をやめさせる
自分では注意せずに、施設管理者を通じて注意してもらいます。
施設管理者へ報告する前や途中で、行政に相談するのも良いでしょう。
パターン4 施設管理者が動いてくれない
施設管理者に、受動喫煙が発生している現状を報告しているのに、改善の手を打ってくれない場合です。
ポイント:施設管理者が、法令の遵守(管理施設内の受動喫煙対策)徹底から逃げてしまっている状態
施策:施設管理者に、法令を守らせる(受動喫煙対策を実施させる)
施設管理者に申し出たのに、改善の手を打ってもらえないのであれば、外部の力に頼るしかありません。
行政へ相談、通報しましょう。
相談、通報窓口

けれども、一体どこに相談、通報すればいいのでしょうか?
相談窓口はどこでしょう?
これに関しては、各自治体で模索を続けている状態ですが、各行政の保健所が対応するのが一般的なようです。
受動喫煙被害を止めるのは、あなた個人の考えや気持ちの問題ではなく、日本の法律の話です。法律を守ってもらうだけの話です。
堂々と相談、通報してください。
なお東京都では、「受動喫煙防止対策に係る相談窓口」を開設しています。
東京都が「相談窓口」を設けています~条例強化・受動喫煙撲滅へ、問い合わせをしましょう
受動喫煙撲滅機構のサポートを受けたい!
受動喫煙撲滅機構では、受動喫煙に悩む方の情報・ご意見を受け付け、また学習・相談 例会 も開催しています。
例会の参加や情報提供は、電話 045-228-8523 もしくは、お問い合わせフォーム から、お問い合わせください。
また、当機構以外の団体も、例会を行なっています。
地域の団体に相談(『 住宅・タバコ問題解決.net.』サイトより。当機構サイトの「リンク」ページにもあります)